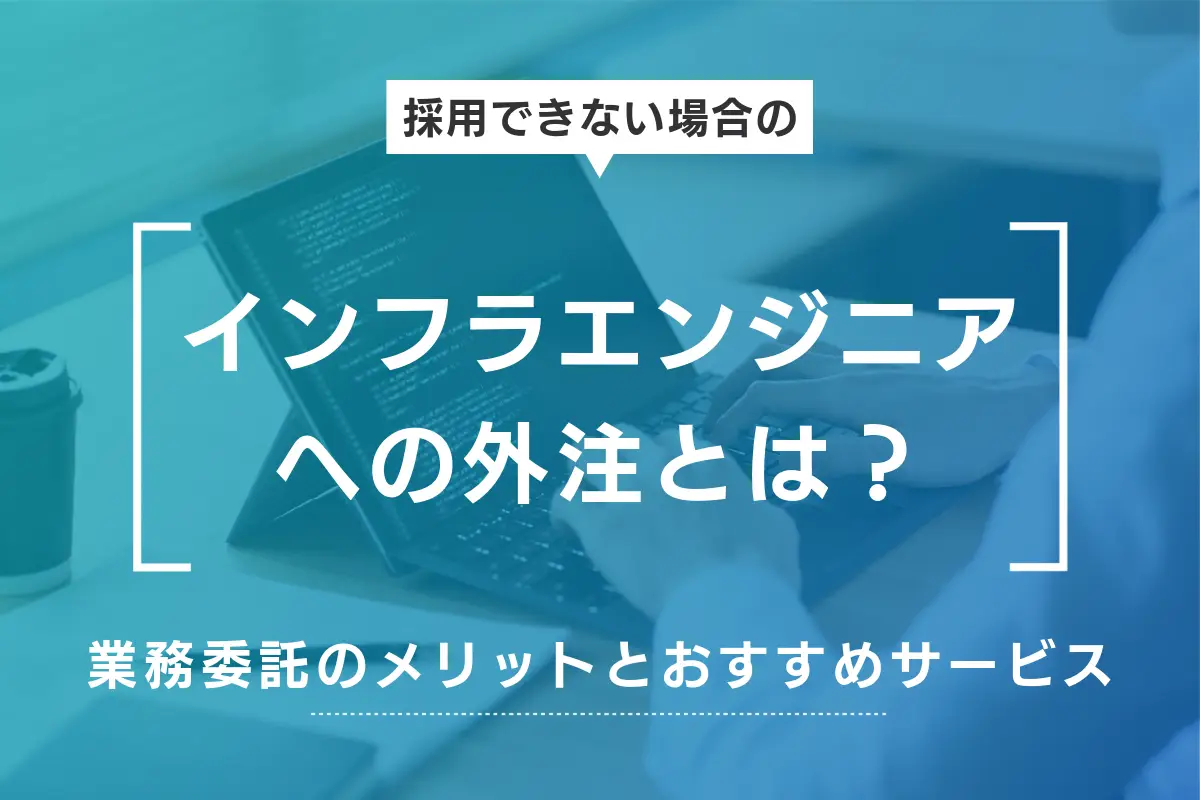
インフラエンジニアを採用するうえで、正社員はメジャーな雇用形態です。エンジニア不足に悩む経営者の方なら真っ先に思い浮かぶでしょう。
しかし「正社員採用が本当に適しているのか」「他に有効な人材確保の手段はないのか」と悩む企業も多いかと思います。盲目に正社員採用にこだわると、人材を有効活用できないかもしれません。
そこで、本記事では以下の内容について解説します。
インフラエンジニアを正社員採用するメリットとデメリット
活躍するインフラエンジニアの特徴
正社員採用の主な手段
正社員以外で人材を確保する方法
本記事を最後まで読めば、正社員でインフラエンジニアを雇用すべきか判断できます。インフラエンジニアの確保にお困りの採用担当者、中小企業の経営者は参考にしてください。
そもそもインフラエンジニアの採用は難しい
大前提として、インフラエンジニアの採用自体が難しいことを押さえておきましょう。雇用形態がどうであれ、採用難の背景を知らないと的外れな採用施策を取る可能性があるからです。インフラエンジニアの採用が難しくなっている主な背景は以下のとおりです。
インフラエンジニアが不足している
スキルが十分でない
待遇が魅力的でない
労働環境が整っていない
<h3>インフラエンジニアが不足している
インフラエンジニアそのものが不足している影響で、どの企業も採用に苦労しています。経済産業省が発表したIT人材の供給動向の予測と平均年齢の推移によると、2030年までに約79万人の高度IT人材が不足するとの試算が出ています。
出典:経済産業省
とくに近年は既存インフラの改修とDXの加速により、インフラエンジニア不足が深刻化しています。加えてIoTやAIの台頭、クラウド技術の普及などITを取り巻く市場も拡大しています。このように、インフラエンジニアの需要減少と市場の成長が人手不足に拍車をかけているのです。
スキルが十分でない
自社が求めるスキルに達していないのも、インフラエンジニアの採用を難しくしています。
インフラエンジニアには高度な専門知識、経験を求められるからです。加えて企業が求めるスキルセットも複雑化しており、ピンポイントにマッチする人材を見つけにくいのが現状。
たとえば、Microsoft Azureに長けた人材が欲しいのに、求職者がハードウェアのバックグラウンドしかなければ活用は難しいでしょう。また、ネットワーク構築の人員が不足しているにも関わらず、フロントエンドのみの経験では機器の設定や配線をこなせるか疑問です。
このようにスキル不足に加えて、採用側とエンジニアの間で求める能力にギャップが生じるケースが多いです。
待遇が魅力的でない
ハイスキルなエンジニアを見つけても、待遇面で敬遠されることもあります。具体的には、以下のような点に不満をもつエンジニアが多くいます。
キャリアアップの機会を得られない
最先端の技術に触れることができない
見込み残業時間が多く休日出勤が多い
企業側に知名度やブランドがない
リモートや出勤などワークスタイルを選べない
企業活動のスピード感に欠ける
総じてインフラエンジニアのマイナスイメージが強い傾向にあります。高収入で柔軟なライフスタイルを好む傾向が強いIT業界では、インフラエンジニアを避ける人は少なくありません。
労働環境が整っていない
インフラエンジニアの労働環境が整備されていない企業は少なくありません。具体的な労働環境の特徴を下の表にまとめました。
インフラエンジニアの労働環境の特徴 | 概要 |
深夜勤務・休日出勤が多い | システム運営を妨げないために、休日夜間にメンテナンスするのが一般的 |
突発のトラブル対応 | ITインフラは24時間稼働しており、不具合が発生すれば深夜や休日でも迅速に対処する必要がある |
問題を解消するまで対処が必要 | トラブルを解消できるまで作業を続けなければいけない |
クラウド技術やリモートワークの普及で、上記の問題は緩和されつつあります。しかし、従来の休日出勤や深夜労働が残っている業務もあるため、応募を渋るエンジニアが一定数います。
関連記事:インフラエンジニアの採用が難しい理由と優秀な人材を獲得する方法を解説
インフラエンジニアを正社員雇用するメリット
インフラエンジニアの採用は難しく、正社員も例外ではありません。それでも正社員を雇用すると、以下のようなメリットを得られます。
長期的にインフラエンジニアを確保できる
時間をかけて育成できる
企業成長の基盤が整いやすい
長期的にインフラエンジニアを確保できる
正社員としてインフラエンジニアを採用すると、長期にわたって人材が定着する可能性が高まります。正社員採用は、組織の将来を引っ張る人材を育てるために行うからです。
豊富な実務経験を自社に蓄積できるので、安定して人材を確保できるでしょう。その結果、継続的な技術継承が可能になり、既存事業の強化や新規事業への展開もしやすくなります。
時間をかけて育成できる
長期の育成を前提にインフラエンジニアを採用できるのも、正社員のメリットです。教育制度さえ整備していれば、オンボーディングの期間をしっかり取ることができるからです。
派遣や契約社員だと長期雇用を見据えないため、離職対策に力を入れるケースは多くありません。しかし、正社員なら定着のためのサポートを充実させると、長期的に見て人材の質が向上します。
最初の1~3年はOJTや研修などで、どうしても周囲の負担が増えてしまいますが、それ以降になると中核エンジニアとして活躍してくれるでしょう。筆者の職場でも新人の育成期間は5年と定めており、6年目移行に現場のチームリーダーに抜擢されることが多いです。
とくに新卒正社員はポテンシャルを見込んで採用されるため、長い目で見ると会社の事業に精通して頼もしい戦力になるでしょう。
関連記事:インフラエンジニアを新卒採用すべき?即戦力人材を獲得する方法も解説
企業成長の基盤が整いやすい
インフラエンジニアを正社員として雇用すると、企業の成長基盤が強くなります。業務委託だと契約の範囲内でしか対応できませんが、正社員なら目の前の仕事に取り組むだけでなく、事業計画や業績など会社の状況も踏まえて対応することができます。
そして、プロジェクトの最終責任は受託会社の正社員にあるはずです。正社員になればその責任の重みを感じ、成長へのモチベーションを高く維持できるでしょう。
また正社員を増やすことで、一部の社員に責任が集中するのを防げるのも特徴。たとえば、マネージャーだけが正社員で他のプロジェクトメンバーが業務委託だと、マネージャーだけが責任を負わなければいけません。一方、一部のSEやプログラマーも正社員にすれば、責任を分散させてコミュニケーションを円滑にすることが可能です。
このように、正社員を増やすと企業成長への寄与はおおきくなるでしょう。
インフラエンジニアを正社員雇用するデメリット
インフラエンジニアを正社員雇用するとさまざまなメリットがありますが、完璧というわけではありません。以下のようなデメリットがあります。
固定費が負担になる
短期離職のリスクが高い
教育・研修が必要
固定費が負担になる
正社員を雇用すると、毎月の給与に加えて社会保険料や福利厚生費用、教育研修費用など数多くの固定費がかかります。また、業務量に関わらず最低限の固定費が必要になるため、利益を圧迫することもありえます。
筆者の職場でも、数か月間のプロジェクトが終わった後に、次のプロジェクト開始まで3か月ほどの空白期間がありました。派遣や外注であれば契約を打ち切ることもできますが、正社員だと自社で待機させるしかありません。
結果として無駄な会議や資料作成が増えたり、必要性の疑わしいプロジェクトの立ち上げなどが起こったりしました。正社員を採用するときは、毎月の固定費と人材の活用手段に対して十分に検討しなければいけません。
短期離職のリスクが高い
正社員を雇用すると、短期離職されたときの損失がおおきくなります。正社員の採用プロセスでは下記のような費用がかかるからです。
面接会場の設営費
説明会の運営費
面接に伴う交通費・宿泊費
内定者研修・懇親会費
内定者の交通費や引越し費用
リファラル採用の一時金
求人サイトへの掲載費
転職エージェントへの報酬
採用サイトやPR広告などの製作費
どれくらい採用活動に力を入れるかにもよりますが、一人当たりの採用コストは新卒で約50万程度と言われています。仮に10人採用するとしてそのうち3人が離職することになれば、150万円の損失になります。
このような短期離職のダメージを軽減するためにも、求職者とのミスマッチを防がなければいけません。
教育・研修が必要
正社員を雇用すると、教育・研修の負担がおおきくなることに注意が必要です。
未経験者や新卒の場合は一から技術を教えなければいけないため、一人前になるのに数年ほどかかります。また経験豊富なエンジニアであっても、自社の経営理念、価値観など企業風土を教え込むにはそれなりの期間が必要です。
OJT、外部の研修、eラーニングなどを活用し、最大限の効果を得られるよう育成計画を立てましょう。
【未経験でもOK】活躍するインフラエンジニアの特徴
ここでは自社で活躍するインフラエンジニアの特徴を解説します。
機械への抵抗がない人
ヒューマンスキルが高い人
異常時対応に慣れている人
ITトレンドに敏感な人
大規模開発の経験が豊富な人
セキュリティに明るい人
雇用形態に関わらずポテンシャルを発揮してくれる可能性が高いので、選考時の参考にしましょう。
機械への抵抗がない人
インフラエンジニアの業務では、サーバーの設置やケーブルの配線、ネットワーク機器の設定など多様な機械を扱うことがあります。メーカーによる仕様の違いにも明るくないといけません。これらの機械操作に抵抗がない人はインフラエンジニアへの適性が高いでしょう。
経験者であれば一定の適性を見込めますが、未経験者の場合は自力でネットワークを作った経験があるか聞いてみましょう。
中古のネットワーク機器を使ってネットワークを構築
クラウドサービスを使って簡単な仮想ネットワークを構築
展示会やイベントなどでサーバー・ネットワーク機器を設営
ITインフラと聞くと大規模なイメージを抱くかもしれませんが、個人で使うレベルのネットワーク構築でも十分戦力になりえます。自主的に取り組んだ実績があれば、仕事への意欲も評価できるでしょう。
ヒューマンスキルが高い人
インフラエンジニアに限りませんが、ヒューマンスキルが高い人も成果を出す傾向にあります。ヒューマンスキルとは、チームメンバーと良好な関係を作るためのスキルのこと。
インフラエンジニアだと技術力の向上に目を向けがちですが、プロジェクトベースで仕事を進める以上、良好な人間関係の構築は不可欠です。とくに上流ポジションにつくと、良好な関係構築に重きを置いているだけでプロジェクト内の空気が良くなります。
下の表のようにヒューマンスキルを細分化しました。応募するポジションや重視する人柄にあわせて見直すと良いでしょう。
主なヒューマンスキル | 概要・特徴 |
ネゴシエーションスキル | スムーズに折衝や交渉を行うスキル |
ヒアリングスキル | 相手の話に耳を傾けて理解・共感するスキル |
リーダーシップ | チームをけん引して目標達成に進むこと |
プレゼンテーションスキル | 自分の主張を的確に伝えるスキル |
コーチングスキル | チームメンバーや後輩を指導・育成するスキル |
コミュニケーションスキル | メンバーへの理解に努めて心理的安全性を生み出すスキル |
異常時対応に慣れている人
突然のトラブルや仕様変更などに動じない人は、インフラエンジニアで力を発揮するでしょう。
大前提として、ITインフラが設計通りに運用できるケースは稀です。たとえば、サービスの人気が急上昇するとサーバーがダウンする恐れがあります。ハードウェアの劣化が想定より進んで、保守工程を圧迫する可能性も否めません。
筆者の職場でも順調にハードウェア検査工程が進んでいたにも関わらず、最終テストで重大なバグを発見したことがあります。チームリーダーは焦らずにクライアントに現在の状況と復旧見込み時期を伝え、現場のメンバーに対処方法を指示しました。
このような経験は机上で身に付けることは難しいため、実務経験が豊富なエンジニアが頼りになります。
ITトレンドに敏感な人
ITインフラを取り巻く技術は常に変化しているので、トレンドに明るい人も重宝されます。
2025年3月時点で押さえておきたいITトレンドは下の表のとおりです。
主なITトレンド(2025年3月時点) | 概要・特徴 |
DX(デジタルトランスフォーメーション) | ITで企業の仕組み自体を変革すること |
AI | 大量のデータを長時間運用 |
IoT(Internet of thing) | モノとインターネットをつなぐ技術 |
5G | 高速・大容量・低遅延を実現できる通信網 |
上記に関連した実務経験があるとプラス評価ですが、なければ関連資格の取得や自己研鑽について質問してみましょう。ポートフォリオで関連の成果(AIロボット開発や職場のDXサポートなど)が記載されていれば、トレンドに敏感と言えます。
大規模開発の経験が豊富な人
大規模開発の経験が多いと、ITインフラの現場で成果を上げやすくなります。大規模開発と聞くと、大企業・官公庁のプロジェクトを思い浮かべるかもしれませんが、扱うデータやアクセス量が多いシステムを指すことも多いです。
近年は中小企業でも、データ量の多いITインフラ構築を求められることも増えました。そのため、大量のアクセスに伴う負荷分散や高速化の仕組みに知見があると良いでしょう。
セキュリティに明るい人
セキュリティに長けたインフラエンジニアであれば、システムの安全性を考慮した設計、構築、運用が可能です。具体的には、以下のようなことを任せるとシステムの安全性を担保できます。
アクセス管理
ファイアーウォールの設定
SSLの導入
パケットの管理・監視
通信の暗号化
ただし、新たなセキュリティ対策をしても、悪意ある第三者がさらに高度な攻撃手法を開発するのも事実です。常に最新のセキュリティ事情をチェックしているか面接で質問してみましょう。
セキュリティトレンドについて勉強したい方は、以下のサイトを参考にすると理解が深まります。
セキュリティ情報取得に | 概要・特徴 |
個人から企業までを対象にセキュリティ啓発を実施 | |
世界各国のセキュリティ政策を紹介 | |
最新のサイバー攻撃の被害事例を掲載 |
正社員のインフラエンジニアを採用する主な方法
正社員でインフラエンジニアを確保する手段は多様化しています。ここでは主な採用ルートを4つ紹介します。
- 転職エージェントの活用
- スカウト採用
- リファラル採用
- 学校訪問
転職エージェントの活用
転職エージェントとは、求職者と企業を繋げる仲介業者のことです。おおきなメリットは採用のミスマッチを未然に防ぎやすいこと。
ハイスキルなエンジニアが見つかっても企業風土や待遇があわなければ、離職されるリスクが高まります。そこで、転職エージェントから客観的な視点で自社の実態を伝えることでフィルタリングしやすくなります。
また、異業種にアプローチしやすいのもメリットです。転職エージェントは豊富な人材データベースを有しているため、自社とは関わりが少ない業界からも人材を探すことが可能です。ただし、転職エージェントの質には幅があるので、エンジニア採用に強みのあるエージェントを選びましょう。
スカウト採用
スカウトとは企業から候補者に直接連絡して、選考へ誘う採用手段です。従来であれば求人広告や採用サイトに募集要項を載せて求職者の応募を待つのが一般的ですが、スカウト採用は真逆になります。
メリットは、優秀なエンジニアに的を絞って採用活動を行えることです。すでに求める人材像が明確なため、スキルや経験の面でミスマッチを起こしにくくなります。
仮に候補者からの応募がなかったとしても、自社の存在を知ってもらうことができます。後に想起されることがあれば、再度の応募につながるでしょう。
注意点としてスカウトはアプローチが一対一になるため、大量採用には向いていません。人員そのものが不足している場合は、転職エージェントも活用しましょう。
関連記事:インフラエンジニアをスカウト採用するメリットや成功させる方法を解説
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員から友人や知人を紹介してもらう採用手段のことです。
メリットは、転職エージェントや求人サイトなどへの費用を削減できること。社員の紹介を通じて候補者を集められるため、採用コストを抑えることができます。社員からの評判次第では、説明会を省いたり選考プロセスを短縮できたりします。
また、社員から仕事内容や社内の雰囲気などの情報を得ているため、入社後のギャップを抑えられるでしょう。
デメリットは、採用活動が長期化するリスクがあること。紹介したい人材が転職活動中とは限らないからです。有力な知人・友人を見つけても応募してもらうためには根気良くコミュニケーションを取る必要があります。また、社員に採用活動の負担がかかるため、通常業務とのバランスも考えなければいけません。
学校訪問
大学や専門学校を訪問し、学生とコミュニケーションを取る採用手段もあります。学
校訪問のメリットは即戦力になりうる新卒を見つけやすいことです。情報系の学部や大学院ではすでに高度な専門スキルを有している学生も多いからです。
私の出身ゼミに在籍していた高度なネットワーク研究をしていた先輩に対し、大手メーカーの採用担当者が直接訪問してきたこともあります。面接のようにコミュニケーションの場が限定されないので、両者のミスマッチが起こりにくいのも魅力です。
また学校側と良好な関係を築けたら、安定して優秀な学生を採用できるでしょう。ただし、優秀とはいえ実務経験のない学生がほとんどです。完全未経験者ほどではないですが、ある程度の育成期間は必要でしょう。
関連記事:インフラエンジニアを新卒採用すべき?即戦力人材を獲得する方法も解説
正社員雇用以外でインフラエンジニアを活用する方法
ここまで読んで、正社員採用はハードルが高いと感じる企業もいるかもしれません。ここでは正社員以外にインフラエンジニアを確保する主な手段を紹介します。
SESと契約
SESとはシステムエンジニアリングサービスと呼ばれ、専門のエンジニアを自社に派遣してもらうサービスのことです。SES企業と契約を結んだらエンジニアを派遣してもらい、自社の指揮下で業務をしてもらうことができます。
メリットは、実務経験が豊富なエンジニアを確保しやすいこと。必要な経験値やスキルセットを決めてエンジニアを派遣してもらうため、即戦力として期待できます。また、プロジェクトの進捗や需要にあわせて人員を調整できるので、人件費を削減しやすくなるでしょう。
注意点として、自社のエンジニアよりコミュニケーションコストがかかる可能性があります。企業文化や価値観が異なるため、プロジェクトの進め方に認識の齟齬が出るかもしれません。自社のメンバー以上に丁寧なやり取りを心掛けましょう。
関連記事:インフラエンジニアのSES採用とは?フリーランスとの比較も解説
フリーランスエンジニアへ委託
フリーランスエンジニアに業務を委託するのも有効な手段です。フリーランスエンジニアとは特定の企業に所属せず個人で仕事をするエンジニアのことで、近年人口が伸びています。
クラウドソーシングサービスのLancersの調査によると、2018年~2021年でフリーランスの人口は500万人以上増加しました。
出典:Lancers:正社員と違って働く場所や時間に柔軟性があることから、フリーランスエンジニアに転向する人が増えているものと推測されます。今後もフリーランス人口が増えることが見込まれるため、優秀なエンジニアを確保する手段として重宝されるでしょう。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
フリーランスでインフラエンジニアを活用するメリット
ここでは、フリーランスエンジニアを活用するメリットを紹介します。
即戦力を期待できる
社外の知見・技術を得られる
人件費を削減しやすくなる
即戦力を期待できる
フリーランスエンジニアは他社での職歴・取引歴が豊富なため、その経験を生かすことができます。未経験者や新卒だとOJTや研修などに時間がかかりますが、フリーランスエンジニアであればすぐにプロジェクトの一員になれるでしょう。
「即戦力なら中途採用でも良いのでは?」と思うかもしれません。しかし将来退職したときに、後任への引継ぎや新入社員への受け入れ準備に手間がかかってしまいます。
一方、フリーランスエンジニアであれば案件の詳細が定義されているため、即座にプロジェクトへの参画が可能です。
社外の知見・技術を得られる
フリーランスエンジニアは多様な企業を渡り歩いているため、社外の知見・技術を得やすくなります。自社だけでは気づけない開発の視点と課題発見につながるため、事業の活性化にも寄与するでしょう。
とくに、客先常駐のように多様なメンバーが顔を会わせる案件では、コミュニケーションの密度が高まります。筆者の職場も外部エンジニアとの交流が盛んで、何気なく教えてもらったメンテナンスのコツがそのまま保守品質の向上につながりました。
このように、フリーランスエンジニアがいれば現場の社員に良い刺激が与えられ、結果として自社技術の向上に貢献するはずです。
人件費を削減しやすくなる
フリーランスエンジニアは、正社員と比べて人件費を削減しやすい傾向にあります。
正社員だと毎月の給料がかかりますが、フリーランスエンジニアはプロジェクトごとに契約を結ぶため、業務量や難易度に応じて報酬を設定することができます。
プロジェクトがひと段落したら契約を解除できるので、閑散期に余分な人件費を払う必要もありません。また、フリーランスエンジニアには福利厚生費用と社会保険料、教育研修費用も不要です。
業務量の波に応じて人件費を適正化したい企業にとって、フリーランスエンジニアは魅力的な人材でしょう。
インフラエンジニア不足にお悩みならクロスネットワークへご相談ください
本記事では、インフラエンジニアを正社員で雇用するメリットとデメリット、主な採用ルートなどについて解説しました。
正社員は、長期的な視点で人材を育成できるため、自社のITインフラが安定しやすくなります。また、継続的な正規雇用が自社の成長のアピールになるので、優秀なエンジニアに興味をもってもらえるでしょう。
一方で雇用調整が難しく、福利厚生や社会保険などの費用が重荷になるのも事実です。未経験者の正社員採用なら、育成コストも負担になるでしょう。
より柔軟に人材を活用するならフリーランスエンジニアへの委託がおすすめです。優秀なエンジニアにITインフラの仮想化を任せるなら、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ITインフラの構築、設計、運用に長けたエンジニアをクライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。






